「子供に習い事をさせたいけれど、繊細で疲れやすいから心配…」
そんな不安を抱える親御さんも多いのではないでしょうか。
HSP/HSC(繊細な子ども)は、繊細だからこそ感受性が豊かで集中力も高い特性があります。
この記事では、その繊細さを活かせる習い事の選び方や、実際に我が家で試して役立った工夫を紹介します。
※本記事では、繊細な子どもを HSC(Highly Sensitive Child)と表記しています。
一般的には「HSPの子ども」と表現されることもあるため、両方の言葉を交えて解説します。
HSC(繊細な子ども/HSP気質の子ども)が習い事で感じやすい不安
繊細な子どもにとって、習い事はワクワクする反面、緊張や不安がつきまとう場面も少なくありません。
友達の動きを気にして表情が曇ったり、大きな声にびくっとして動きが止まったり…。
「できなかった」と感じると心がいっぱいになり、涙ぐんでしまうことも。
そんな姿を目の前にすると、習い事は楽しみであると同時に、大きな負担になり得るのだと改めて感じます。
周りの子と比べてしまう
HSC(繊細な子ども)は、周りをよく見ているからこそ「自分と他の子の違い」に不安を感じやすい傾向があります。
我が子も体操の時間になると、隣の子の動きをじっと見て「自分はできていない」と落ち込むことがよくありました。
たとえ小さな差でも気にしてしまい、楽しむよりも不安が大きくなってしまうのです。
親から見ると「よく頑張っている」と思える場面でも、本人にとっては劣等感につながりやすいと実感しました。
大きな声や音に疲れやすい
HSC(繊細な子ども)の習い事では、大きな声や音に圧倒されて疲れてしまうことがあります。
我が子の場合も、先生の大きな掛け声や音楽のボリュームにびくっとして動きが止まってしまうことがありました。
その場では頑張ろうとするのですが、終わったあとにぐったりと疲れ切ってしまい、「もう行きたくない」と言うことも。
楽しませたいと思って選んだ習い事なのに、環境の刺激で逆に負担になってしまうのだと気づかされました。
できないことがあるとすぐ不安になる
HSC(繊細な子ども)は、ちょっとした「できない」経験でも自信をなくしてしまうことがあります。
我が子も体操の動きで一度つまずくと、「できない」「もう無理」と口にして涙ぐんでしまうことがありました。
周りの子ができている姿を見ると、さらに不安が膨らみ、自信をなくしてしまうのです。
親としては「少しずつで大丈夫」と伝えたいのに、本人にとってはその瞬間が大きな壁に感じられるのだと気づかされました。
HSC(繊細な子ども)の習い事は、楽しみである反面、強い不安やプレッシャーを感じてしまうこともあります。
だからこそ、最初の一歩は「どんな習い事を選ぶか」よりも「子供の性格や興味をどう尊重するか」が大切になります。
子供の性格や興味を優先する
HSC(繊細な子ども)の習い事では、周りに合わせて無理をしてしまうことが少なくありません。そこで我が家では「楽しそうに続けられるか」を基準に選ぶようにしました。
- 内向的な子には少人数制やマンツーマン
周りに気を遣わず、安心して取り組める環境が合いやすい。
さらに、自宅で取り組める通信教材も「人目を気にしない」点で相性が良いです。
- 体を動かすのが好きな子にはスポーツ系
走る・跳ぶといった活動でエネルギーを発散できる。
特にスイミングや体操は、体力を発散しながら自信につながりやすい習い事です。
ただ、大人数での練習だと周りの声や雰囲気に圧倒されてしまう子もいます。 - コツコツ型の子には音楽や工作などの積み重ね型
少しずつ上達していく過程を楽しめる。
特にピアノは、練習の積み重ねが成果につながりやすく、
達成感を実感しやすい習い事です。
【椿音楽教室】ならマンツーマンレッスンで、
子どものペースに合わせて優しく指導してもらえます。
繊細な子でも安心して取り組める環境が整っているので、
初めての習い事としてもおすすめです。
HSC(繊細な子ども)の習い事でも、まずは「好き・安心できる」を基準にすると長く続きやすいと感じています。
親が安心して通わせられる環境かをチェックする
子供が楽しめるかどうかに加えて、親自身が無理なく続けられるかも大切なポイントです。
送迎の負担や教室の雰囲気、保護者同士の関わり方など、実際に通う立場になって考えてみることで、長く続けやすい習い事を選ぶことにつながります。
- 教室や先生の雰囲気を確認する
子供だけでなく、親もリラックスして通わせられる雰囲気かどうかを見ておくと安心です。 - 送迎の負担をイメージする
毎週通うことを考えると、距離や交通手段、時間帯が無理なく続けられる条件かどうかが重要です。 - 保護者同士の関わり方を知っておく
待合室の雰囲気や保護者の交流の有無など、実際に通う親の立場から気になる点もチェックしておくと安心です。
見学や体験を通して雰囲気を肌で確かめる
パンフレットや口コミだけでは分からない部分はたくさんあります。
実際に体験に参加してみて、子供の反応や教室の空気感を肌で感じ取ることが大事だと分かりました。
我が子も体操教室の体験では、周りの子の声や先生の指導に敏感に反応し、帰宅後にぐったりしてしまったことがあります。
その経験から「子供の気質に合った雰囲気かどうか」を事前に確かめることの大切さを痛感しました。
- 先生やスタッフの接し方を見る
子供への声かけやサポートの仕方が、安心感につながるかどうかをチェックしましょう。 - 子供の反応を観察する
体験中の表情や帰宅後の様子から、本当に楽しめているかを判断するヒントになります。 - 教室全体の雰囲気を感じ取る
音やにおい、待合室の様子など、写真では分からない空気感を肌で感じておくことが大切です。
体験の場での刺激が強いと感じやすい HSC(繊細な子ども)は、少人数や静かな時間帯を選ぶと負担が減ります。
わが家の体験談
最初に選んだのは、保育園内で行われていた体操です。
送り迎えの負担がなく、友達と一緒にできるので「これなら無理なく続けられる」と思いました。
ところが、我が子はHSC(繊細な子ども)の特性が強く、周りの子の動きや先生の声かけに敏感に反応してしまいます。
「できていない」と感じるとすぐに不安になり、体操の時間を終える頃にはぐったりしてしまうことも。
楽しい時間のはずが、むしろ疲れてしまう場面が目立つようになりました。
そこで思い切って、少人数制の教室に変えることにしました。
人数が少ない分、先生のサポートも手厚く、子供のペースを尊重してもらえる環境。
そのおかげで以前のように不安でいっぱいになることは減り、少しずつ笑顔で通えるように変わっていきました。
この経験を通して、子供の性格や気質に合った環境を選ぶことの大切さを実感しています。
まとめ
HSC(繊細な子ども)は、繊細だからこそ環境の影響を強く受けやすい反面、集中力や感受性といった大きな強みも持っています。
HSC(繊細な子ども)に合う習い事は、繊細さを理解し、安心できる環境を選ぶことから見つかっていきます。
もし合わないと感じたら、無理に続ける必要はありません。
子どもに合った習い事を探す過程そのものが、親子にとって大切な経験になります。
繊細さを弱みと捉えず、その特性を活かせる習い事を見つけてあげられるといいですね。
FAQ
-
HSPの子どもの習い事は何から始めればいい?
-
まずは少人数・体験可・静かな環境を条件に、短時間から。自宅で試せるオンライン体験も相性が良いです。
-
HSCとHSP、表記が違うと選び方は変わる?
-
呼び方が違っても「繊細さに合う環境を選ぶ」点は同じ。この記事ではHSCを基本として解説しています。
-
HSPの子どもに向いているスポーツは?
-
進行がゆっくりで指示が明確なスイミングや小規模体操など。体験で音量や雰囲気も確認しましょう。

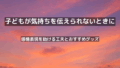
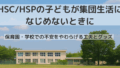
コメント